今回読んだ本「知識を操る超読書術」メンタリストDaiGo
読書術について知りたいと思った理由
この本を手に取ったのは、これから読書をするときに、本の知識をちゃんと吸収したいと思ったからです。
私は本を読んで「勉強になった!」と思っても、しばらく経つと忘れてしまい、いつももったいないと思っていました。
このブログを書きはじめたのも、本を読んで感じたこと、学んだことをまとめておきたいというのが理由の一つです。
これまでなんとなくで読書をしてきた私が、ちゃんと知識を得る読書をするために、「知識を操る超読書術」から学んだことをまとめます。
「知識を操る超読書術」から学んだこと
この本から私が学び、これからの読書に生かそうと思っているのは以下の3つです。
読む前に、本を読む目的を明確にする
ひとつ目は読む前に目的を明確にすること。
私は目的はなんとなく持って読む本を選んでいますが、「本の中から読むべき箇所を判断する」や「熟読の対象か手早く読む対象か明確に分ける」ことはしていませんでした。
読み終わって、「参考になる知識が手に入っていればいいな〜」という程度。
でも大切なのは読む前に、この本から得たい知識を「明確」にすること。
「なぜこの本を読もうと思ったのか」
「この本から何を得たいか」
「読んだ後どんな状態になりたいと願っているか」
著者が読書で何よりも大切と言っているのがこれです。
読みながら、自分の関連する記憶や体験を探る
二つ目は、読みながら、書かれている内容を自分の経験に置き換えること。
自分の体験と結びついてインプットされると、記憶に残りやすくなるそうです。
確かに、自分には難しい経済の本を読んだとき、自分と関連づくことがなさすぎて、ただ字を目で追ったのようになり、なんとか読み終わったけど、何も記憶に残っていなかった…ということがあります。
自分の体験と結びつかなくて、記憶に残らなかったかも。
少しでも自分の経験や記憶と結びつけていれば、少しは記憶に残っていたかもしれません。
アウトプットでは単純化する
得た知識を誰かに話すときは、誰でもわかるくらい単純化すること。
伝えたいたった一つが伝わればいいと割り切ること。
先に書いたように、私は本の備忘のために、このブログを書き始めました。
記事を書いていて、忘れたくない箇所全てを書こうとして、「ここもよかった、ここもここも」と書こうとしてしまい、最後は何が何だかわからなくなっていることが多々あります。(というかこればかり)
古典に挑戦、意外に読めた!
この読書術を読んでから、読んでみようと思ったのが、「孫子の兵法」です。
今まで、古典なんて難しくて理解できないから絶対読めない!と思っていました。
でも上記の3つ、特に「目的を決める」をしたので、自分の欲しいところ以外や難しいところは読み飛ばして読みました。そうすると古典も意外とサクサク読み進めることができました。
アウトプットは以下の記事にまとめています。
この読み方なら読書の幅が広がりそう
これからの読書では、この読書術を使い、読書で得た知識をさらに役立てていきたいと思います。
もともと読書は好きですが、敬遠していた古典でも(飛ばしながらなら)読める、自分に役立てられると分かったので、他にも色々と読んでみたいと思いました。
興味を持ったら、自分に役に立ちそうなところだけでも読む。
これなら、もっといろんな知識が本から得られそうです。
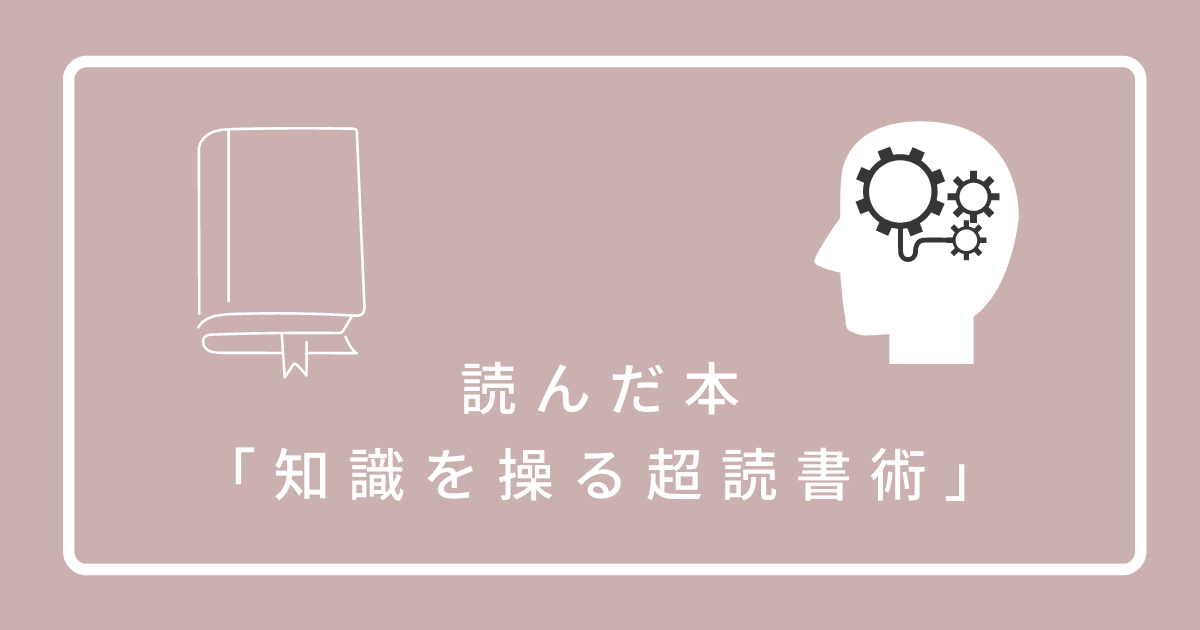
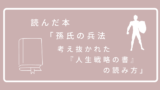
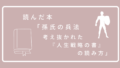

コメント