今回読んだ本「読書について(光文社古典新訳文庫)」ショーペンハウアー
意味ある文章とは何か?
私は読んだ本の備忘のためにこのブログを書いています。
今回読んだ本、「読書について」を書いたのは、ショーペンハウアー先生、ドイツの哲学者です。
そのまま書いたわけではなく、ショーペンハウアー先生が書いた『余録と補遺』という作品の中から、いかに文章を書くべきか、いかなる本を読むべきか、というテーマに対して書かれた3篇をまとめたものです。
このうち1篇目、「自分の頭で考える」を読んだ時は、私の『読書好き』の部分にグサグサと刺さる内容でした。(多読ダメ…)
読み進めて2作目、『著述と文体について』では、いかなる本を読むべきが、が書かれていて、私の「ブログに文章を書いている」の部分にグサグサ刺さりました。
とても丁寧な綺麗なお言葉で、サクサクッと刺してくるので、もう文章なんて書けない…とも思ったのですが、それでも(懲りずに)文章を書くために、これは心がけるようにしようと思った内容についてまとめます。
「著述と文体について」から学んだこと
「著述と文体について」から、文章を書くのはこのブログ程度の私が学んだ、これから気をつけたいことが以下の3つです。
書くのは伝えるべきことがあるから
書くべきテーマがある人だけが書くに値することを書く。
ただ紙を埋めるために書いているのはすぐにバレるそう…
私にしか手に入らない素材を探す
ありふれた凡庸な人でも、その人にしか手に入らない素材を取り上げれば、素材のおかげで大変重要な本を生み出すこともある。
私にしか手に入らない事柄を書くなら、まだいいよってことでしょうか…先生
賢いふりをしない
ありふれたことでも、実際に考えたことをそのまま伝えようとするなら、読むに堪える本になる。引き伸ばせば本当は一体何が言いたいのか分かりにくことがよくある。
確かに、大学のレポートでも作文でも、文字数を稼ごうと引き伸ばして、結局何を書いてるか自分でもわからなくなったことが何度も。
自分に書けることを書く…しかない
文章を書く時には、自分の考えたことで、相手に伝えたいことを、気取らずありのままに書く。
ありふれた凡人(私)が書く時は、この方が「読むに耐える」ようです。
私は本を書くわけではないですが、ブログに文章を書く時にも、30代、女性、会社員、未婚、そういう今の自分が考えたこと、感じたことという素材について、賢ぶらずに書く、これしか出来ない…。
読むべきではないものは投げ捨てろ!
読むに値しないものが大量に出回っていて、読むべきではない本だと気づいたら、投げ捨てなさいと先生は仰います。(笑)
読むに値するものを書くなんて到底出来ませんが、本ではなくブログなので投げ捨てられることもないですし、自分の頭で考えたものを書く、ということは最低限心がけて、細々とブログを書いていこうと思います。
文章を書く方には強いメンタルの時に読んでもらいたい本でした。
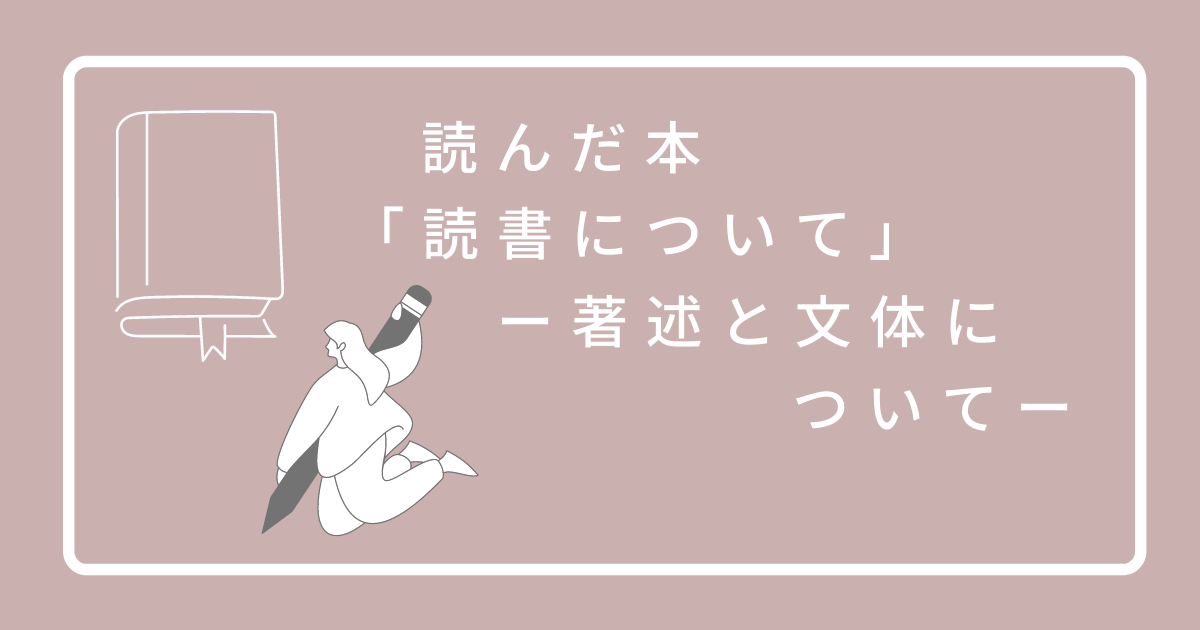
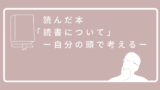
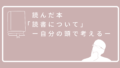

コメント