今回読んだ本「方丈記」著者 鴨長明 訳者 蜂飼耳
なんか疲れた
コロナ禍で変わるこれからの生き方・働き方、お金のこと、仕事のこと、人間関係のこと…
最近、なんか疲れた。
そんな時に「ゆく河の流れは絶えずして」で始まる「方丈記」を思い出しました。
私は学生のころ教科書でこの文を読んで、その時に「なんかいいな」と感じていました。
このざわついている、こんがらがっている頭を整理したい。
この世の儚さを読むことでちょっと気分が変わらないかな。
そんな思いから、「方丈記」を読んでみました。
全文を読むのは初めてでしたが、400字詰め原稿用紙20枚程度の長さで、すぐに読めます。
読んでみて、世間から離れることが、安らかな心を手に入れるポイントと感じたのでまとめます。
どうすればこの身と心を安らかにさせておくことができるのか?
方丈記は、「ゆく河の流れは絶えずして」で始まる随筆(エッセイ)です。
著者(鴨長明)は、いつでも簡単に移築できる草庵で山に隠れ住んでいて、気に入っているそう。
そんな長明先生の暮らしから、私の心に響いたものを3つ記載します。
騒がしい世界から距離のある小さな住まい
『都に出かけると自分が落ちぶれたと感じるが、帰宅しほっと落ち着くと、他人が俗塵の中を走り回っているのが気の毒になる。』
長明先生でも、やっぱり騒がしい社会の中にいると、自分を落ちぶれたと感じるらしい。
でも気に入っている小さな家に帰るとホッとする。
私もどちらかといえば、自分に合った小さめの家がホッとする。それなのに、テレビでのお家紹介や知人の新居に招かれるたびに、心がざわざわする。
騒がしい世の中との物理的な距離を取るというものも、心を安らかに保つには必要ということなのだと思いました。
都会の真ん中で暮らして、心穏やかにできる人はすごい。
ひとときを楽しく過ごす繋がり
『山の麓に男の子が住んでいて、ときどき遊びにくる。年齢はだいぶ違うがひとときを楽しく過ごそうという点では通じ合う。』
私はコロナ禍になって、仕事の付き合いの飲み会などがなくなって、「なければない方が絶対いいな」と感じています。
コロナ禍では友達に頻繁に会うことも無くなったけど、実はあんまり悲しいとかはない。
たまに会ったり連絡したり、ひとときを楽しく過ごすことができる。そんな友人とのつながりは切れないように大切にしていこう。
物への執着
『そのときどきに得られたものを食べて、命をつなげればいい。人に会うわけではないから、自分の身なりを恥ずかしく思うこともない。』
最近は、空腹の大切さも色々なところで言われています。
またTPOに合わせた色々な服装も、世俗の暮らしの中にいなければ必要のないもの。
今の生活を保つためにかかるお金は本当に欲しいもの、私の望みに繋がっている?
周りに溢れているから、ついつい手に入れたくなっているのでは?
ミニマリストの皆さんがものを無くすのも、ものと物理的な距離を取ることで執着から解き放たれるためなのかも。
悩みは私がこの場所で生きている限り続きそう
著者曰く、『世間近くに住むということがどういうことか知っている。もう何かを望むこともないし、あくせくすることもない。ただ、静かに暮らすことだけを考え、余計な心配のないことそのものを楽しんでいる。』
この文章に対する私の感想、「いいなぁ」
私は世間の中に住み、色々と望んで、あくせくしています。
本当は、色々なものと距離をとって暮らしたい。でも今の生活を捨てれずにこの場所にいる限り、悩みは絶えないのかもしれません。
著者がこの最終的な移動式の住居に済んだのは60歳(54歳かもしれない)の頃。
30代の今の私は、色々なものと距離をとって暮らす決断はできません。なんだかんだで、今の生活を選んでいるのも自分です。
いつかのためにも健康第一
私にはまだ著者のような暮らしはできない。
山で山菜で生きる力はないし、狭い賃貸で暮らすにも、どんなに質素な食べものも着る物も、全くお金がかからないわけではない。
でも穏やかな生活って、そこまで構えなくてもできるものなのかもしれない。
世間と離れて暮らす、それだけでも安らかな生活は準備万端にしなくても得られる。
ものやらお金やらはなくても著者のような生活はできるかもしれないけれど、「健康」だけはないと穏やかな暮らしができないと感じたので、いつかのために、仕事のストレスで鬱になるような生活だけは絶対やめようと思います。
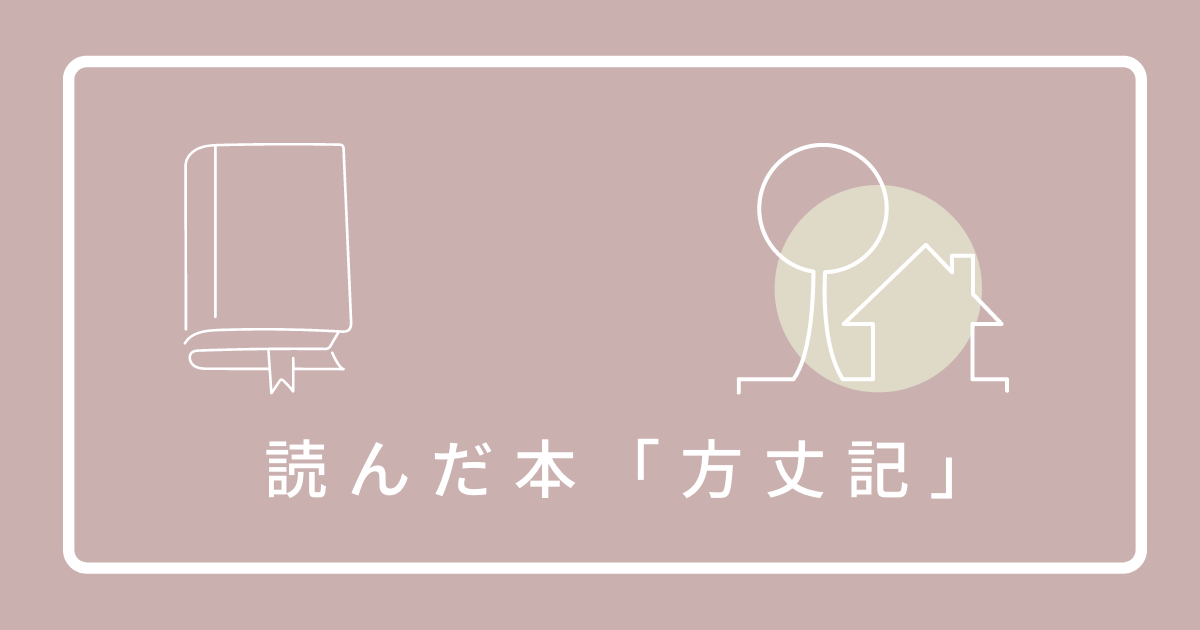
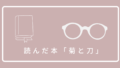

コメント